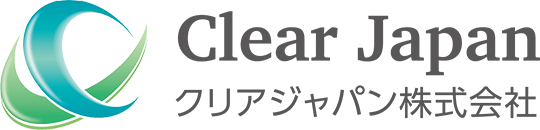コラム
原状回復工事・店舗内装解体|クリアジャパン株式会社【全国対応】
-
[営業時間]9:00~18:00
大分県中津市豊田町6-20 AXIS ONE 1F-A
- 御見積無料
- 0979-53-9330
原状回復工事の費用相場を詳しく解説|工事の流れや発注方法も

オフィスの移転や店舗の閉店が決まり、原状回復工事が必要になった。
しかし、「一体いくらかかるのか、見積もりが適正なのか分からず不安だ」「法外な費用を請求されるのではないか」といった、多くの事業者が直面する切実な悩みを抱えてはいないでしょうか。
原状回復工事は、多額の費用が発生する可能性がある一方で、その内容や費用構造は非常に専門的です。知識がないまま進めてしまうと、本来支払う必要のない費用まで負担させられるリスクも少なくありません。
この記事をお読みいただければ、原状回復工事の費用相場はもちろん、コストを適正化するための具体的な交渉術、信頼できる業者の見極め方まで、意思決定に必要な全ての知識が手に入ります。
そしてこれにより、不安を解消し、自信を持ってプロジェクトを推進できるようになります。
本記事は、数多くの商業施設の原状回復工事を手掛けてきた弊社クリアジャパンの知見に加え、国土交通省が公表する『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』の内容をもとに、客観的かつ専門的な視点から執筆しています 。
目次
1.そもそも原状回復工事とは?費用の基本を理解しよう
具体的な費用の話に入る前に、原状回復工事の定義と、誰が何を負担するのかという大前提を明確にしましょう。この基本原則を理解することが、後のトラブルを未然に防ぎ、不必要な出費を避けるための第一歩となります。
原状回復工事の定義と重要性

まず最も重要な点として、「原状回復」とは「入居時と全く同じ新品同様の状態に戻すこと」ではありません 。
法律上、そして国土交通省のガイドラインが示す考え方では、原状回復とは「借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。
つまり、普通に使っていて自然に古くなったり汚れたりした部分(通常損耗・経年劣化)まで、全て元通りにする義務はないのが原則です。
なお、オフィスや店舗といった事業用物件における原状回復工事は、単に部屋を綺麗にする以上の目的を持っています。
- 次のテナントへの円滑な引き渡し: 物件をリセットし、次の事業者がスムーズに入居・開業できる状態にする。
- 資産価値の維持: 貸主(オーナー)にとって、建物の価値を維持し、将来的な賃貸経営を安定させるために不可欠。
- 契約上の義務の履行: 賃貸借契約書に定められた義務を、借主として誠実に果たす。
この定義を正しく理解することが、後述する費用負担の交渉において極めて重要になります。
(参考)国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版):https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html
【重要】貸主・借主の負担範囲は契約書とガイドラインで決まる
原状回復費用の負担範囲を決定づけるのは、法律(民法)、賃貸借契約書の「特約」、そして国土交通省のガイドラインという3つの要素です。
その優先順位は原則として「法律 → 特約 → ガイドライン」となりますが、それぞれの関係性を理解することが不可欠です 。
借主負担(特別損耗): 借主の故意・過失による損耗
借主が費用を負担するのは、故意(わざと)や過失(うっかり)、または通常とはいえない使い方によって生じた損傷です。これらは「特別損耗」と呼ばれます。
【借主負担となる具体例】
- 壁に物をぶつけて開けてしまった穴
- タバコのヤニによる壁紙の著しい変色や臭いの付着
- 床に重量物を落としてできた深い傷や凹み
- 飲み物などをこぼしたまま放置してできたシミやカビ
- 清掃を怠ったことによる水回り(キッチン、トイレ)の頑固な汚れやカビ
- (契約で許可されている場合でも)ペットがつけた柱の傷や臭い
貸主負担(経年劣化・通常損耗): 自然な劣化や通常使用による損耗
一方、時間の経過とともに自然に発生する劣化(経年劣化)や、契約通りに通常の使用をしていて生じる損耗(通常損耗)の修繕費用は、原則として貸主が負担します。これらのコストは、毎月の賃料に含まれていると考えられているためです 。
【貸主負担となる具体例】
- 日光による壁紙やフローリングの色あせ
- 家具の設置による床やカーペットの軽微な凹み、設置跡
- ポスターなどを留めるための画鋲やピンの穴
- テレビや冷蔵庫の裏の壁にできる黒ずみ(電気ヤケ)
- エアコンや給湯器など、設備の耐用年数経過による故障
以下の表は、貸主負担と借主負担の一般的な例をまとめたものです。見積書をチェックする際の参考にしてください。
| 部位 | 貸主負担(経年劣化・通常損耗)の例 | 借主負担(特別損耗)の例 |
|---|---|---|
| 壁・天井 | 日照によるクロス変色、画鋲の穴、テレビ裏の電気ヤケ | タバコのヤニ汚れ、落書き、ネジ釘の穴、結露を放置したカビ |
| 床 | 家具の設置跡、日焼けによる色あせ、通常使用による摩耗 | 引っ越し作業でつけた傷、重量物による凹み、飲みこぼし等のシミ |
| 設備 | 設備の耐用年数経過による故障(エアコン、給湯器等) | 手入れを怠ったことによるキッチンの油汚れ、風呂場のカビ |
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の重要性
ここで重要な役割を果たすのが、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です 。
このガイドラインは、元々は居住用賃貸住宅のトラブル防止を目的として作成されたものですが、オフィスや店舗のような事業用物件に関する明確な公的指針が存在しないため、裁判所の判例などにおいても、
貸主と借主の負担割合を判断する際の「社会通念上、合理的な基準」として広く参照されています 。
特約の注意点: オフィス・店舗契約における最重要ポイント
事業用物件の契約で特に注意が必要なのが「特約」の存在です。
契約書に「通常損耗や経年劣化についても借主の負担で修繕する」といった特約が記載されている場合、ガイドラインの原則よりもこの特約が優先されることが多くあります 。
しかし、この特約が常に万能というわけではありません。
2020年4月に施行された改正民法では、貸主が通常損耗を借主に負担させる特約を設ける場合、その内容を契約時に明確に示し、借主がそれを理解した上で契約することが求められるようになりました 。
つまり、契約書に曖昧な文言で記載されているだけ、あるいは契約時に十分な説明がなかった特約は、消費者契約法上の不当条項として無効と判断される可能性も残されています 。
この「契約書の特約」と「ガイドラインが示す合理的な基準」の間の緊張関係を理解することが、不当な請求に対する交渉の鍵となります。
2. 【費用相場】原状回復工事にかかる具体的な費用

ここからは、事業者の皆様が最も知りたい具体的な費用相場について解説します。
費用は物件の規模、グレード、業態、内装の状態によって大きく変動するため、「坪単価」と「工事内容別の単価」の両面から把握することが重要です。
事務所・オフィスの坪単価別費用相場
オフィスの原状回復費用は、規模が大きくなるほど、またビルのグレードが高くなるほど坪単価も上昇する傾向にあります。
これは、大規模・ハイグレードなビルほど、空調や防災設備が複雑であったり、使用されている建材が高品質であったり、工事に際しての制約(夜間工事指定など)が厳しくなったりするためです 。
| オフィス規模 | 坪数目安 | 一般ビル | ハイグレードビル |
|---|---|---|---|
| 小規模オフィス | ~30坪 | 3万円~8万円 | 5万円~10万円 |
| 中規模オフィス | 30~100坪 | 5万円~12万円 | 8万円~15万円 |
| 大規模オフィス | 100坪~ | 8万円~20万円 | 15万円~40万円以上 |
上記の金額はあくまで目安です。間仕切り壁の数や特別な造作の有無によって、費用は大きく変動します。
店舗(飲食店・物販など)の坪単価別費用相場
店舗の原状回復費用は、業態によって大きく異なります。
特に飲食店は、厨房設備や給排気ダクト、グリーストラップといった専門設備の撤去・清掃が必要になるため、他の業態に比べて高額になるのが一般的です 。
| 業態 | 坪単価相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 飲食店(重飲食) | 8万円~20万円 | 厨房、排気ダクト、グリーストラップ等の撤去で高額化 |
| 飲食店(軽飲食) | 5万円~10万円 | 重飲食よりは安いが、水回りや排気設備の撤去は必要 |
| 物販・小売店 | 3万円~8万円 | 内装の造作が少なければ比較的安価 |
| 美容室・サロン | 3万円~15万円 | シャンプー台など水回り設備の撤去が費用を左右 |
| クリニック | 3万円~8万円 | レントゲン室など特殊な設備がなければ他店舗と同等 |
また、退去時の状態として「スケルトン返し(建物の構造躯体だけの状態に戻す)」を求められる場合は費用が最も高くなります。
一方で、次のテナントに内装や設備をそのまま引き継ぐ「居抜き」での退去交渉が成功すれば、工事費用をかなり抑えることも可能です。
【内訳】工事内容別の費用単価表
提示された見積書が適正価格か判断するために、工事項目ごとの単価相場を把握しておきましょう。
「一式」という曖昧な表記ではなく、各項目が単価と数量で明記されているかを確認することが重要です。
| 工事内容 | 単位 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| クロス張替え | m2 | 1,000円~1,800円 | 量産品か高機能品かで変動 |
| 床タイルカーペット交換 | m2 | 2,500円~4,500円 | |
| 塗装工事(壁・天井) | m2 | 800円~2,000円 | |
| 内部造作・間仕切り解体 | 一式 | 10万円~ | 規模、材質による。m2単価の場合もある |
| 電気・照明工事 | 一式 | 5万円~ | 照明器具の撤去・交換、配線整理など |
| 設備(空調・防災)工事 | 一式 | 10万円~ | 専門性が高く、B工事に指定されやすい |
| ハウスクリーニング | m2 | 500円~1,500円 | 専門業者による清掃 |
| 産業廃棄物処理費 | 一式 | 3万円~ | 解体物の量と種類による。m3単価の場合もある |
3. 【コスト削減】原状回復工事の費用を安く抑える4つのコツ
費用相場を理解した上で、次はコストを具体的に削減するための実践的な方法をご紹介します。受け身で請求を待つのではなく、能動的に動くことで費用は大きく変わります。
① 相見積もりを必ず取る

原状回復工事の費用を適正化するための最も基本的かつ効果的な方法は、必ず2~3社から相見積もりを取ることです 。1社だけの見積もりでは、その金額が高いのか安いのかを客観的に判断できません。
相見積もりを比較する際は、総額だけでなく、以下の点を重点的にチェックしてください。
- 内訳の細かさ: 「内装工事一式」のような曖昧な項目ではなく、「クロス張替え 〇〇m2 単価〇円」のように、工事内容、数量、単価が詳細に記載されているか。詳細な内訳を提示しない業者は注意が必要です 。
- 数量と面積の正確さ: 見積書に記載されている施工面積(m2)は、実際の面積と合っていますか。不必要に広い面積で見積もられていないか確認しましょう。特に、契約面積(壁の中心で計算する「壁芯面積」)ではなく、実際の工事対象となる「内法面積」で計算されているかどうかもポイントです 。
- 諸経費の内訳: 「現場管理費」や「諸経費」といった項目が、工事費総額の10%~20%程度の妥当な範囲に収まっているか。不明瞭な一式計上になっていないか確認しましょう 。
- 不要な工事の有無: 本来は貸主負担である「経年劣化」部分の修繕や、入居時よりも良い状態にする「グレードアップ工事」が含まれていないか、厳しくチェックします 。
② ビル指定業者とB工事の確認
オフィスビルの工事には、費用負担者と業者選定者の組み合わせによってA工事・B工事・C工事という3つの区分があります。この区分を理解することが、コスト削減の大きな鍵となります。
-
A工事【費用負担:貸主、業者選定:貸主】
ビルの躯体や共有部分など、建物全体の基本構造に関わる工事。
-
B工事【費用負担:借主、業者選定:貸主】
空調、防災設備、防水など、借主の専用部分でありながら建物全体に影響を及ぼす工事。
-
C工事【費用負担:借主、業者選定:借主】
内装仕上げ、電話・LAN配線、什器設置など、借主が自らの責任と費用で自由に行える工事。
ここで最も注意すべきは「B工事」です。借主が費用を負担するにもかかわらず、工事業者は貸主が指定した業者しか使えません 。そのため競争原理が働かず、費用が相場よりも高額になりがちです。これが「B工事の罠」とも言える構造的な問題です。
この状況を打開するための交渉戦略は以下の通りです。
- まず、貸主(または管理会社)から提示された工事区分リストを入手し、どの工事がB工事に該当するかを正確に把握します。
- B工事とされている項目について、C工事を依頼できる自社選定の業者からも参考見積もりを取得します。
- その参考見積もりを基に、貸主側に対して「指定業者の見積もりは相場より高すぎる」と具体的な根拠を示して価格交渉を行います。
- 最終的な目標として、安全性に問題がない範囲で、B工事の一部をC工事に変更してもらうよう交渉します 。
これが認められれば、借主が自由に選んだ業者に競争力のある価格で発注できるようになり、大幅なコスト削減が期待できます。
③ 居抜き退去を検討・交渉する
「居抜き退去」とは、設置した内装や設備を解体・撤去せず、そのままの状態で次のテナントに引き継いで退去する方法です。これが成功すれば、原状回復費用を大幅に削減することも可能です 。
メリット
- 解体・撤去費用の大幅な削減 。
- 工事期間が不要なため、退去までのスケジュールに余裕が生まれる 。
- 次のテナントから内装や設備の「造作譲渡金」を受け取れる可能性がある。
デメリット
- 貸主の承諾が絶対条件であり、必ず認められるとは限らない 。
- 後継テナントを自ら探す必要がある場合がある。
- 貸主側は、設備の瑕疵(不具合)などを巡る後継テナントとの将来的なトラブルを懸念し、居抜きに消極的なケースも多い 。
貸主の承諾を得やすくするためには、日頃から物件を綺麗に使い、多くの業態で利用しやすい汎用的な内装を保っておくことが交渉を有利に進めるポイントになります 。
④ 不要な工事項目がないか精査する
見積書を最終チェックする段階では、賃貸借契約書と国土交通省のガイドラインに立ち返り、本来負担する必要のない工事が含まれていないかを徹底的に精査します。
以下の質問を自問自答しながら、見積書の項目を一つひとつ確認してください。
- 「この修繕は、契約書で定められた自分の義務の範囲内か?」
- 「これは自分がつけた傷(特別損耗)ではなく、貸主が負担すべき経年劣化・通常損耗ではないか?」
- 「廊下や給湯室、トイレといった『共用部分』の修繕費用が、誤って含まれていないか?」
一つでも疑問に思う項目があれば、遠慮なく業者や貸主側に説明を求め、納得できるまで交渉することが重要です。
4.原状回復工事の流れと信頼できる業者の選び方

ここでは、実際に工事を発注してから完了するまでの具体的な流れと、後悔しないための信頼できる業者の選び方を解説します。
発注から工事完了までの6ステップ
- 賃貸借契約書の再確認
退去の意思を固めたら、まず契約書を隅々まで読み返し、「解約予告期間(通常6ヶ月前など)」と「原状回復義務の範囲」を正確に把握します。 - 業者選定・現地調査依頼
複数の業者(最低2~3社)に連絡を取り、物件の状況を直接確認してもらう「現地調査」を依頼します。 - 相見積もり・業者決定
各社から提出された見積書を、前述のチェックポイントを基に比較検討します。価格だけでなく、提案内容の質、担当者の専門性や対応の速さも総合的に評価し、発注先を決定します。 - 貸主(管理会社)への工事申請・承認
選定した業者と確定した工事内容を貸主側に報告し、工事の承認を得ます。B工事の交渉などもこの段階で最終決定します。 - 工事着工
スケジュールに基づき工事を開始します。着工前に近隣のテナントへ挨拶回りを行うのがマナーです。 - 工事完了・引き渡し
工事が完了したら、貸主または管理会社の担当者立ち会いのもとで仕上がりを入念にチェックします。指摘事項がなければ、鍵を返却し、物件の引き渡しが完了となります
失敗しない業者選びの4つのポイント
適正価格で質の高い工事を実現するには、信頼できる業者選びが最も重要です。以下の4つのポイントを必ず確認してください。
Point1:実績の豊富さ
自社が借りている物件の業態(オフィス、飲食店、物販店など)や規模、立地(商業施設内など)と類似した工事の実績が豊富にあるかを確認しましょう。
特に、弊社のように大型商業施設内の原状回復工事を数多く手掛けている業者は、施設特有の厳しいルールや貸主側との複雑な交渉にも精通しており、スムーズな進行が期待できます 。
Point2:見積書の透明性
「一式」という言葉でごまかさず、工事項目ごとに単価や数量が明確に記載された、透明性の高い見積書を提出してくれるかどうかが重要です 。
見積もりの不明点について質問した際に、ごまかさずに論理的かつ丁寧に説明してくれる業者を選びましょう。
Point3:担当者の対応
問い合わせに対するレスポンスは迅速か、専門的な質問に的確に答えられるか、こちらの要望に対して親身に相談に乗ってくれるかなど、担当者のコミュニケーション能力や誠実さも重要な判断基準です 。
コスト削減につながるようなプロ目線の提案をしてくれる担当者は、信頼できるパートナーとなり得ます。
Point4:各種許認可の有無
コンプライアンスの観点から、業者が法的に必要な許認可を保有しているかの確認は必須です。これは業者の信頼性を担保する最低条件です。
建設業許可
500万円以上の工事を請け負う場合に必須となる許可です。
国土交通省が運営する「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、許可の有無や有効期限を誰でも確認できます 。
産業廃棄物収集運搬業許可
解体工事で発生した廃棄物を自社で運搬・処分するために必要な許可です。無許可の業者に依頼すると、依頼主(借主)も不法投棄の責任を問われる可能性があります。
この許可は、環境省所管の「産業廃棄物処理業許可 行政情報検索システム」で確認可能です 。
これらの公的なデータベースで事前に確認することで、無許可業者との契約リスクを回避できます。
5.原状回復工事のよくある質問(FAQ)
最後に、原状回復工事に関してよくある質問をQ&A形式でお答えします。
- 高すぎる見積もりを提示されました。どうすればいいですか?
- まずは慌てずに、本記事で紹介した単価表やチェックリストを参考に、見積書の内訳を精査してください。
「不要な工事」や本来「貸主が負担すべき項目」が含まれていないかを確認します。その上で、他社から取得した相見積もりを具体的な根拠として提示し、論理的に価格交渉を行うのが有効です。
交渉が難航する場合は、弁護士など法律の専門家への相談も検討しましょう 。 - 敷金はどのくらい返ってきますか?
- 預け入れた敷金(保証金)からは、①原状回復工事費用、②未払いの賃料、③その他契約に基づく費用(清掃費など)が差し引かれ、その残額が返還されます。
したがって、原状回復費用を適正な金額に抑えることが、敷金の返還額を最大化するための最も直接的な方法となります。 - 工事期間はどのくらいかかりますか?
- 物件の規模や工事内容によりますが、一般的な目安として、小規模オフィス(~30坪)で1週間~2週間、中規模オフィスで2週間~4週間程度です。
大規模な物件や、特殊な解体・設備工事が必要な場合は1ヶ月以上かかることもあります。賃貸契約の解約日から逆算し、余裕を持ったスケジュールで業者選定を始めることが極めて重要です。 - どこまで掃除すればいいですか?
- 通常、原状回復工事の見積もりには、専門業者による「ハウスクリーニング」費用が含まれているのが一般的です。
そのため、借主自身が業務用の洗剤などを使って大掛かりな清掃を行う義務は通常ありません。ただし、私物や事業で使った備品、ゴミなどは全て撤去しておくのが契約上の義務でありマナーです。 - 貸主との交渉が決裂しそうです。どこに相談すればよいですか?
- まずは契約を仲介した不動産会社や、日常的にやり取りのあるビルの管理会社に間に入ってもらうのが第一歩です。
それでも解決が難しい場合、法律に基づいた交渉が必要になる可能性がありますので、弁護士への相談が適切です。
近年、原状回復費用の削減をうたうコンサルティング会社も存在しますが、弁護士資格を持たない者が報酬を得て法律事務(交渉代行など)を行うことは弁護士法で禁じられた「非弁行為」にあたる可能性があるため、依頼先の選定には注意が必要です 。
なお、法テラスなどの公的な無料法律相談窓口もありますが、事業用の案件は相談対象外となる場合があるため、事前に確認することをお勧めします 。
(参考)法テラス:https://www.houterasu.or.jp/
6.まとめ
本記事では、オフィスや店舗の原状回復工事に関する費用相場からコスト削減のコツ、信頼できる業者の選び方までを網羅的に解説しました。最後に、重要なポイントを改めてまとめます。
- 原状回復の定義: 借主の故意・過失による損耗を修復する工事であり、「新品に戻す」ことではない。
- 費用負担の原則: 負担範囲は賃貸借契約書の「特約」が優先されるが、不当な内容は国交省のガイドラインを基準に交渉の余地がある。
- 費用相場: オフィスの坪単価で3万円~20万円以上と幅広く、ビルのグレードや内装、店舗の業態によって大きく変動する。
- コスト削減の鍵: 「相見積もりによる比較検討」と、高額になりがちな「B工事」の内容を精査し「C工事」への変更を交渉することが極めて重要。
- 業者選び: 実績や見積もりの透明性に加え、「建設業許可」などの公的な許認可を必ず確認することが、信頼できるパートナーを見つけるための絶対条件。
原状回復工事は、専門的な知識が求められる複雑なプロジェクトです。
しかし、正しい知識を身につけ、信頼できるパートナーを選べば、費用を適正化し、スムーズに退去手続きを完了させることが可能です。
もし、あなたがオフィスの移転や店舗の原状回復でお悩みなら、まずは専門家にご相談ください。
弊社クリアジャパンは、全国の商業施設における豊富な実績と交渉力で、お客様に最適なソリューションをご提案します。無料のお見積もりやご相談から、まずはお気軽にお問い合わせください。